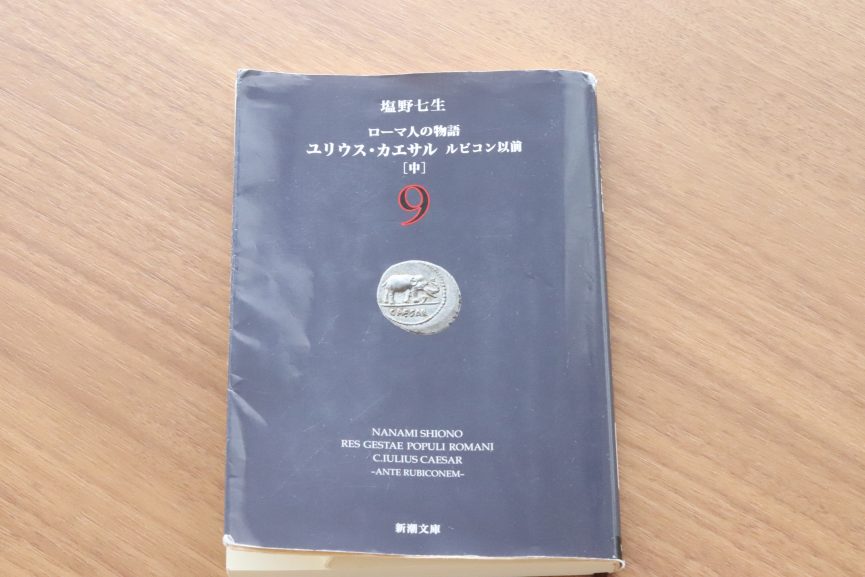こんにちは、Portafortuna♪光琉です。
「ユリウス・カエサル ルビコン以前 ローマ人の物語Ⅳ」③
ガリアは現フランス・ベルギー・オランダ・ルクセンブルグ・ドイツ・スイスという広範囲な地名を指し、乱暴に言うとケルトです。「ガリア」はローマ人の呼び方で、もとは確かギリシア語やったと思います。
そのガリアにイギリスも加えた地方をカエサルが制覇していったのが八年にもおよぶガリア戦役です(五年の任期だったのが途中で延長されます)。
ガリア戦役の詳細については、カエサルが自ら書いた「ガリア戦記」が残されていて、その客観性については研究者も太鼓判を押すそうです。それで塩野さんもこれに沿って話を進めます。「ガリア戦記」はもともとは元老院への報告書としてカエサルが書いたものなんだそうです。
塩野さんがまず着目するのは、カエサルがいきなり本題から書き始めている点です。前書きも導入部もなくいきなり本題から入る。どんなにすごい物書きでもそんなことはできず「マイッタ」となるそうです。物書きじゃない僕には「ふ~ん、そんなもん?」でしかありませんが、物書きの塩野さんが言うんだからそうなんでしょうね。カエサルはなぜ前書きも導入部もなく本題から書き始めたのかについては、キケロや小林秀雄の言葉を引用してその理由を挙げてくれている塩野さん。でもここからが難しい。カエサルは前書きや導入部を書かなかっただけでなく書けなかったのではいか?と続けます。
「達意の文章家である彼のことだから、技能的に書けなかったのではない。もっと別の理由で書けなかった、のではないかと思う。それについては、彼が北伊と南仏とイリリアの三属州の総督に、なぜ五年間もの任期を望んだのかも合わせて考えれば、肉薄も可能になるのではないかと思う。」
この話ここで打ち切りなんです!肉薄も可能、うん、どういうことなんかな?と思って読み進めても塩野さん答えを書いてくれてないんですよ~、意地悪やわ~。「読者よ、自分なりに考えてみよ」と言わんばかり。それで僕も将棋風に言うと長考してみたんですが、さっぱり思いつきませんでした。文庫版第九巻、この読書感想文を書くにあたって実は5回読み返しました。そのたびにここで長いこと立ち止まって考えているんですがわかりません。でも苦し紛れに考えたことを書きます、たぶんチャランポランな答えです。カエサルはガリア戦役終了後にいよいよ政体改革に乗り出す気でいたんだと思うんです。そうなるとカエサル対元老院の内乱が起こる、内乱は不可避と読んでいたのではないか。でもガリアに赴任する前のカエサルにはポンペイウスとは違い自分に忠誠を誓ってくれる兵士、子飼いの兵士たちがいない。そのような兵士たちをもつにはやはり長い時間苦楽を共にする必要がある、ちょうどポンペイウスが海賊一掃作戦さらにはオリエント制圧をしたのと同じように。五年という時間はそのための時間であり、さらに戦役を通して兵士たちに実地訓練させ、精鋭に仕立て上げるのにも必要な期間と考えていたのではないか。さらに平定後のガリア全体を自派に組み入れようとしていたのではないか。先ほども書いた通りガリア戦記は元老院への報告書です、ある程度書いてはローマに送って、また書いてはローマに送っていたんだと思います。それならば、まさか前書きや導入部に「ガリア戦役の真の目的は元老院体制を打破して新政体を樹立することにある」なんてこと書くわけにはいかなかった、すなわち書けなかったということになるのかな~と考えてみました。
カエサルは私益のためだけにガリアを平定しようとしたわけではありません。カエサルによると、ガリアに赴任する三年前からある兆候が見られていたとのことです。スイス・アルプスに源を発し、現代では六か国を流れて北海に注ぎ込むライン河、これを境界に西側はガリア、東側はゲルマニアとされていました。西側のガリアは
「現代からは想像もつかないほどに未開発で、森林と沼と河川のほうが、耕地よりはずっと大きな部分を占めていた。ただし、水が豊かなうえに気候も厳しくはない。」ことから人口を賄える農産物・家畜を産することができていました。「勢力の強い部族ならば十以上、小部族までふくめれば百近くの部族に分立しており、統一には遠いのが、紀元前一世紀のガリアの現状であったのである。」
当時のガリアは、豊かとまでは言えなくとも食べるものにも困るというようなこともなく、百近い部族が勢力争いをしつつも均衡を保っていたという状況でした。そのガリアにとっての脅威は
「ライン河の東側の森の奥深く棲む、ゲルマン人であったのである。ラインの西方とちがって、同じく森と沼でも、ラインの東方では気候が厳しい。増える一方の人口を養っていけるだけの、食糧を調達できる手段が充分でなかった。食べていけなくなった人々の眼が、食べていける地方にそそがれるのは自然の勢いである。ライン河を越えての「蛮族侵入」は、食糧調達が厳しくなるたびにくり返される恒例行事のようになっていた。」
「まったく、西ヨーロッパにとってのゲルマン民族の脅威は、二千年このかた変わらなかったのかと思うと笑ってしまう。このゲルマンの侵攻を比較的にしても容易にしたのは、統一や団結を得意としないガリア人の性向にもあった。」
たしかに、笑っちゃう。ガリア人ってほとんど現フランス人でしょ、統一や団結を得意としないってそのまんまやん。ドイツもフランスもずっと一緒やな。
部族間で争うことをやめないガリア人たちは、敗色濃厚となるとゲルマン人に助けを求めていたこともゲルマン人がガリアに侵入する要因の一つになっていました。
ガリア人たちさ~、自業自得やん。
ライン河を越えてのゲルマンの侵入に耐え切れなくなったのが、レマン湖の東方に住んでいたヘルヴェティ族=現スイス人でした。ゲルマンと闘って敗れたへルヴェティ族は、部族全員でガリア西部のブリターニュ(ブルターニュ)地方へ逃げ出すことを決めます(実際にはブリターニュというよりそのすぐ南に位置する現在のペイドラロワール地方じゃないのかな?と思います)。戦闘要員九万二千を含む三十六万八千人の大移動です。未練がないように自分たちの住んでいた町と村を焼き払っての移動ですから本気度が伺えます。スイスからブリターニュへの移動です、真っすぐ西に向えれば良かったのですが、その間には強力な部族の居住地帯が並びます。そこを通過するということは戦いになることも考える必要がありました、なにせ三十七万の人間が通過するのですから。それでヘルヴェティ族はスイスからいったん南下し、ローマの南仏属州を西に向かって通り過ぎ、オーヴェルニュ地方からまた北上するという、道程を取ろうとします。そこで南仏属州の通過許可を赴任前のこととてまだローマにいる次期属州総督カエサルに求めました。しかしカエサルは拒否します。三十七万もの人間の移動がスムーズにいくわけがなく、治安の悪化が予想される。それに、ブリターニュに移動と言ってもブリターニュにはすでにいくつもの部族が長く住みついていて、ヘルヴェティ族が移動するということはそこでの戦闘は避けられない。戦闘になればそれがガリア各地に広がり多くの難民が生じる。その難民は豊かで混乱のない南、すなわち南仏属州に向うことは目に見えている。それでカエサルは拒否したのでした。困ったヘルヴェティ族は闘いも辞さない覚悟で真っすぐ西に向おうとしますが、実際に向かう前、準備の段階ですでに問題が起こり始めていました。それでヘルヴェティ族は再度南に向おうとします。この報告をローマで聞いたカエサル、壮行会もほどほどに急ぎガリアに向います。ガリア戦役の始まりです。
この文庫第九巻では八年におよぶガリア戦役の五年目までが語られます。部族名もたくさん登場して混乱するし、戦闘の逐一をここで追っても長くなり過ぎるので、概要と印象に残った箇所について書きます、備忘録ですから。
ガリア戦役一年目
古代の地中海世界では戦争は春から秋にかけて行うもので冬は休戦期になります。ガリア戦役一年目も紀元前五八年の春から初秋にかけて遂行されました。
もともと親ローマ派であったガリアのヘドゥイ族と共闘し、同じくガリアのヘルヴェティ族=現スイス人との闘いに勝ったローマ。カエサルはヘルヴェティ族に元の地=現スイスに帰るように命じます。カエサルのもとに戦勝の祝辞を述べに訪れたガリア諸部族の長たちは集まってガリア会議を開催、その会議の結論をカエサルに報告します。
「要約すれば、ガリアに代わってゲルマンをたたいてくれ、につきる。」
ガリア会議の議長はヘドゥイ族の長だったので、塩野さんはカエサルが裏で糸をひいていた可能性があると踏んでいます。ガリアが不安定なのはゲルマンが侵入してくるからだ、ローマがなんとかしてくれないと第二第三のヘルヴェティ問題が起こるという論理です。属州総督は、担当属州に治安上の問題がない限り元老院の了承なく他国と剣を交えることは許されていません。カエサルにしてみれば、部族長達が言うように今後も同じような問題が起こる可能性があるし、部族長たちに頼まれたのだからこのままガリア戦役を続行するよと元老院に報告できるということです。カエサルは公然とガリアに介入できることになりました。塩野さんの読み通りカエサル絶対裏で糸をひいていましたね。策士ですよね。
ということでガリア戦役一年目の後半はゲルマンの頭目を敵にしての戦いになりました。それでも初めは話し合いで解決しようとしたカエサルですが、平行線に終わります。でも、ここでも元老院に対して「話し合いで解決しようとしたけど相手が聞く耳をもたなかったから、仕方なく戦闘を行った」と報告できるわけですよね、さすが策士。ゲルマンの頭目を相手に鮮やかに勝ったカエサル、ガリア戦役一年目を終えます。
「敵への不信だけでできる戦争とはちがって、政治は、敵でさえも信頼しないことにはできないのである。」
まるで信頼できないプーチンを相手に政治はできないわけだ、トランプさん早く気づけよ。
「戦争は、死ぬためにやるのではなく、生きるためにやるのである。戦争が死ぬためにやるものに変わりはじめると、醒めた理性も居場所を失ってくるから、すべてが狂ってくる。生きるためにやるものだと思っている間は、組織の健全性も維持される。」
第二次世界大戦中の日本ですね。
「彼(カエサル)は、部下を選ぶリーダーではなかった。部下を使いこなす、リーダーであった。」
格好いいな~。もっとも、部下を選ぶ時点でもうそのリーダーはダメでしょうけど。
勇猛勇敢で知られるゲルマンを相手に闘う前に、ローマ軍は臆病風におかされます。ガリアの商人たちからゲルマンたちの恐ろしさを吹聴されたからです。兵士を集めたカエサルは叱咤激励しましたが、その演説の中で「戦いに勝つには、不屈の意志こそが最上の武器であることは明らかだろう。」と言います。良いこと言うな~カエサル。ガリア戦記の中のこのくだりについて塩野さんは「アイロニーとユーモアを行間に漂わせる文章力、絶品である。」と絶賛しています。そして、この時の演説全体を評して「人心把握の技の極を示して、言葉もない。これでは、女相手にだって成功するはずである。」とします。実際に成功しまくりましたよね、カエサル。
「人間には、誰かに後事を託さねばならない場合、こと細かに指示を与えて託す人と、任務は与えても細かい指示までは与えないで託す人の二種に分れる。全幅の信頼を置くがゆえか否かは、ほとんど関係ない。前者は、自分自身が細かに指示を与えられるほうが仕事がしやすい人であり、後者はその反対であるにすぎない。カエサルは完全に後者に属した。」
ここ読んですっきりしました。僕は完全に前者です。こと細かくがんじがらめに指示されないと何もできません。
ガリア戦役一年目すなわち紀元前五八年、ローマでは三頭派のクロディウス(旧クラウディウス)がキケロへの復讐に執念を燃やしていました。キケロはカエサルに「どうしたものか?」と相談します。
「それにしても、クロディウス台頭の仕掛人であること明らかなカエサルに相談するとは、キケロの人の良さにはあきれ返るしかない。」
なかなか面白いやんキケロ、天然入っとる?
カエサルは、ガリアに来たら幕僚の一人に任命してあげるからガリアでほとぼり冷ましたらええやんと誘った(そうなったらローマから遠ざけられる、カエサルの思うつぼ)のですが、感謝しつつも断ったキケロ。同い年のポンペイウスが最後は助けてくれると思っていたみたいです。ここでも人が良すぎるキケロ。
クロディウスに過去の話を蒸し返されたキケロは、ローマを追放されて遠くギリシアまで渡ります。元老院派の他のメンバーもポンペイウスも一般の市民も皆キケロを見捨てたのです。
「もともとが手紙魔だったキケロは、このときの追放中に、おびただしい数の手紙を各地に送っている。・・・(中略)・・・そのすべてが、追放の身を嘆き、早くローマに帰れるよう取りはからってくれと頼む内容で共通している。」
このことから付けられた綽名が「泣き虫キケロ」。キレ者ではあったけれど「逆境には弱かった」キケロも「人間的」ではあったんですね。
ガリア戦役二年目
紀元前五七年は、現ベルギー・オランダ南部・フランス北東部に住むベルガエ人=現ベルギー人が相手でした。ガリア人の中でも最も戦闘的だとカエサルは書き残しています。
ベルギー人の諸部族を相手に戦ったのですが、何回読み返しても何故戦ったのか僕にはよくわかりませんでした。双方とも本当に戦う必要あったの?避けられやんだんやろか?ガリア南部はとうの昔からローマの属州になっている、中央部は前年ローマに屈している、だから今年は自分たちが住む北東部にローマが進軍してくるだろうとベルギー人たちは考えて戦いの準備を始めた。そしたらその不穏な動きをキャッチしたローマも受けて立つみたいな感じで進軍した。そして実際に戦闘が始まった。のようにしか思えない。それこそまず話し合いとかせんの?「ローマは別に北東部に攻め入る気ないけど、あんたらなんでそんなローマとやる気になっとんの?あんたらやる気あるみたいやからローマも準備しとんのやけど?お互い止めやん?」とかできやんだんやろか?
いずれにしてもカエサルはベルギー人相手でも次々と勝利していきます。その中でアドゥアトチ族を攻めた時です。ローマ軍の技術力に恐れをなしたアドゥアトチ族は講和を求め、ローマは受け入れます、平和になりました。が、講和した日の夜中にアドゥアトチ族はローマ軍を急襲します。しかし結局ローマは勝利。四千人が殺され、他は戦闘員も住民も全て奴隷として売り飛ばされました。
「ローマ人は、その中でもローマ人であることを強く意識するカエサルは、誓約をことのほか重要視する。・・・(中略)・・・たとえ異人種でも対等の人間と認めるがゆえに、交わされた誓いを信ずるのである。・・・(中略)・・・戦いを起こすこと自体は、カエサルにしてみれば罪ではなかった。しかし、いったん交わした誓約を破り攻めてきたことは、明らかに罪に値したのである。人間であることを放棄した者には、彼にしてみれば、奴隷がふさわしい運命だった。」
カエサルの考えもわかるんですが、アドゥアトチ族の中でも誓いを破って急襲することに反対した人きっとおったやろうと思うんですが、その人たちも奴隷に売り飛ばされたと思うと不憫でしょうがない。
ガリア戦役二年目の報告書を受け取った元老院は、十五日間もの神々への感謝祭を決議しました。ガリア戦記の中でカエサルは「これまで誰一人として与えられなかったことである」と品を保ちつつも行間に虚栄心を漂わせて書いています。
「虚栄心とは、他人から良く思われることを喜ばしく思う心情である。」一方、野心は「他者に良く思われなくてもやりとげなくてはならない想い」であると塩野さんは言います。そしてカエサルは人一倍虚栄心が大きかったものの、野心はさらにもっともっと大きかったと続けます。偉人とは言え人間ですからね。
ガリア戦役二年目、紀元前五七年は、元老院派が巻き返しをはかった年でした。執政官二人のうちの一人を元老院派が占め、キケロの国外追放も解除され、早速帰国します。元老院派は三頭の離反を画策します。と言っても「クラッススは無視してもかまわないから、離反を策すのはポンペイウスとカエサルの間であった。」哀れなクラッスス。元老院はポンペイウスに食糧庁長官という名目ではあっても実際には海軍の総司令官という職を与えてポンペイウスを釣ります。そして気を良くしてやる気を取り戻したポンペイウスはローマでは初となる常設劇場「ポンペイウス劇場」の建造にとりかかります。元老院の巻き返しがうまくいっていた一年でしたが、首都ローマの都心の治安は悪化していました。元老院派・民衆派それぞれを名乗った暴力組織が跋扈し、流血騒ぎが日常になっていたからです。首都の治安も維持できないほど元老院派の統治能力は地に落ちていたわけです。
紀元前五六年四月(三年目のガリア戦役が始まる直前)、カエサル提案による「ルッカ会談」がトスカーナ地方のルッカ(カエサル担当の属州にある小さな町)で行われます。カエサル・ポンペイウス・クラッススの三頭による会談です。四年前とは違い公然と開催されたルッカ会談には元老院議員全六百人のうち二百人もが駆けつけ、その中には国家の要職に就いている人たちも多数含まれていました。
会談では紀元前五五年の執政官にポンペイウスとクラッススが立候補すること、紀元前五四年からの五年間は属州総督としてポンペイウスはスペインに、クラッススはオリエントに派遣されること、カエサルの三属州総督の期間もさらに四年延長すること(計九年)、三人に与えられる兵力も各十個軍団(六万人)にすることなどが決められました。実力者三人が決めたことです、さらにカエサルの連戦連勝はローマ中を熱狂させていました。三頭で決めたことは元老院でも市民集会でもすんなり可決されました。
キケロは三頭の思うままになったのは「元老院派の不決断と低能さ」が原因だと嘆きますが、キケロもその元老院派の一人、どころかその筆頭です。ローマ史上最高の知性の持主キケロは「自己批判は得意な男ではなかった。」この人が出世できたのはなんでなんやろ?不思議。
ガリア戦役三年目
紀元前五六年のほとんどは、ガリア西部ブルターニュ地方からペイドラロワール地方の制覇に費やされました。前年恭順を誓ったにもかかわらず、ヴェネティ族に扇動され反旗を翻したガリア西部の諸部族を相手にした年でした。結局海軍まで編成して勝利したカエサルは、主犯格のヴェネティ族に対しては厳しく臨みました。長老たちは死刑、住人全員は奴隷に売り払いました。「野蛮人どもに以後、外交関係を尊重しないことの誤りを悟らせるため」と書いています。でもな~、そもそもローマの侵略戦争やからな~。ガリア人にも言い分があるやろな~。
「彼(カエサル)は、ガリア人の宗教や風俗習慣を叙述しながらも、それらが自分たちのものより劣っているなどとは、一言も言っていない。それどころか、彼ら特有のもの、つまり文化は、尊重している。」
でも尊重するのと支配するのは別の話、なわけねカエサルさん?
「経済の進出は文明の進出でもある。進出された側がしばしば神経質に反応するのもそのためである。」
神経質に反応するのは、それを横で見ている第三者もですね。
ガリア戦役四年目
紀元前五五年は、センセーショナルな年です。まず、ローマ人として初めてライン河を渡ってゲルマニアに侵攻します。ついでこちらもまたローマ人として初めてドーヴァー海峡を渡ってブリタニアに侵攻します。
ゲルマン同士の戦いに敗れ押し出される感じでガリアに侵攻してきたゲルマンの弱小二部族、カエサルとの話し合いの最中に起こった事故のようないざこざから戦闘に発展、ローマは圧勝します。ガリア戦役一年目に続いて二回目のゲルマン人相手の大勝でした。
「ガリア人がほとんど負けてばかりいたゲルマン人だったから、ローマ人による二度の大勝が、ガリア人に与えた影響は大きかったであろう。」
そして「プロパガンダの重要性を、当時では他の誰よりも理解していた男だった」カエサルは史上初めてライン河に橋をかけてゲルマニアに侵攻することを考えました。流れの速いライン河に橋をかけるなんてことはそれまで誰も考えたことがなかったのです。高い技術力を駆使し、資材到着からわずか十日で橋を完成させたローマ軍。ゲルマンたちは恐れをなして森の奥深くに逃げ込みました。戦闘らしい戦闘もなく二部族を屈服させたカエサルは、目的は達成できたとし、ガリアに戻ります。橋は渡った後で破壊しました。
ガリアに戻ったカエサルは、続いてブリタニア侵攻を決めます。ガリアを常に支援していたのがブリタニアだったため、それを断ち切るためでした。とは言え、戦争に適した季節も終わりに近かったこともありこの時のブリタニア侵攻は小規模なもので、ほとんど実地踏査のようなものでした。
順風を待ってガリアから出港したカエサル「翌日の午前十時、最初のローマ船がブリタニアの海岸に達した。ウィンストン・チャーチルが、大英帝国の歴史はこのときよりはじまる、とした紀元前五五年八月二十六日である。」
ヨーロッパの礎はローマ文明にあるんだと思われて興味深いです。とは言えチャーチルさん、カエサル以前のご先祖様たちに失礼っちゃう?でも、ヒットラー率いるドイツ国民のことを「ラインの向うの非文明の民」というのが常だった人らしいからそんなもんか。
地中海と違い気候が厳しいブリタニア、潮と風に流されて予定していた地点から遠く離れた場所に接岸したり、係留していた船が波にさらわれたり破壊されたり、なかなか戦上手なブリタニア人たちからの抵抗もあったりで、実地踏査としてならば成功した程度の成果をあげただけでその年はガリアに戻り、冬営に入りました。
しかし、ガリア戦役四年目の報告を受けたローマは前例のない二十日間もの神々への感謝祭を決めたほど熱狂しました。
この冬営期間中にカエサルは、ガリアに来て以来ずっと信頼しかわいがっていた「青年クラッスス」を手放すことになります。あのクラッススの長男です。父親と違い大変有能な青年でしたが、「ルッカ会談」で決められた通り、父クラッススは翌年から五年間シリア属州総督として赴任します。その父に尽き従っていかなくてはならないからです。常に騎兵不足にさらされていたカエサルですが、しかしその五分の一にあたる一千騎を青年クラッススに分け与えて送り出します。さすがカエサル、度量が違う。
この頃からカエサルは首都ローマの都市改造計画に着手します、私費で。ローマの一等地中の一等地に大邸宅を構えるキケロがあきれかえるぐらいの金を使った改造計画です。今や世界の首都になったローマの中心部は、建国当初と変わらぬ規模でした。さすがに手狭になっていたのでそれを拡張しようという改造計画です。ここで一つ疑問が湧いてきます。ガリアに出向く前からカエサルは天文学的借金をかかえていました。さらにガリアでは私費を投じて兵士を増員しています。若い頃から融資してくれていたクラッススは、シリア属州総督赴任を控え人に融資できる状態ではない(相変わらずローマ一の金持ちでしたが、シリアでは隣国の大国パルティアとの戦争が待っておりその準備に私財を投じる必要があったため)。カエサルの資金はどこにあったのか?塩野さんは、制覇しつつあったガリアでの利権をビジネス化したのではないかと考えています。ローマの商人がガリアで商売する際にピンハネしたんだろうと。このころからカエサルは借金をするどころか人に貸すようにもなったそうです。ちゃっかりしてるな~。でも、
「民族の文明化とは、キケロの見事な散文やカトゥルスの情感したたる韻文によるよりも、経済によることを知っていた。それがためにカエサルは、ガリアとの通商を積極的に奨励したのである。」ここでもカエサルは私益と公益を両立させているわけですね。
ガリア戦役五年目
紀元前五四年は、ガリア戦役始まって以来カエサルが初めて大打撃を受ける年になります。
前年とは打って変わって五個軍団3万と騎兵二千を連れたカエサルはブリタニアに再上陸します。どういう状況?と僕には頭が追いつきませんが、兵士を載せた五百七十八隻の後ろには商人を載せた船二百隻が同行したんだそうです。いやいやいやまだ制覇したわけっちゃうし、それどころか今から戦争しに行く、要するに殺しに行くっちゅうのに、なんでこのタイミングでそんなにたくさんの商人がついていくわけ?戦争に勝って強奪してくるつもりか?それとも無理矢理買わせるつもりか?ひくわ。
ブリタニアに上陸したローマ軍ですが、この年も最初の敵はブリタニア人ではなく悪天候。暴風雨のせいでまたもや係留中の船に大きな損害を受けてしまいます。
ブリタニア側は今年もローマが攻めてくるだろうと諸部族が一致団結して待ち構えていました。初めこそローマ軍の数に驚いて内陸部に逃げたブリタニア勢でしたが、地の利を活かしてゲリラ戦で対抗してきました。が、カエサルの粘り強い作戦に結局は屈服します。戦いに適した季節が終わろうとしていたのでカエサルはガリアに引き上げました。
秋分の頃ガリアに戻ったローマ軍は、ガリアでの冬営準備にとりかかりました。しかし、この年紀元前五四年は小麦の収穫が悪く、総勢四万五千もの兵士の食糧を一地方で賄うことは不可能でした。そこでガリアに来て初めて七か所に分散して冬営することになりました。
嫌な予感しますね。反撃のチャンスとみたガリアの一部族エブロネス族がローマに反旗を翻します。サビヌスとコッタの二人で率いている冬営地を急襲したのです。しかし、簡単にローマに蹴散らされました。蹴散らされてからが巧妙でした。自分たちのような弱小部族がローマに反旗を翻したのは他部族にそそのかされたからである。ゲルマン人がライン河を越え大挙してこちらに向かっている。他の冬営地で冬営している他部隊と合流したらどうか。こう言うのもカエサルに恩があるからだと告げたのです。貴族のサビヌスは敵の進言を受け入れようと、平民のコッタは反対をしました。二人以外の幹部たちもほとんどが反対でした。しかし、貴族のサビヌスに遠慮したコッタが最後の最後には折れて冬営地を捨てることになりました。案の定です、移動中のこの隊をエブロネス族が取り囲み、武装解除すれば命は助けると騙して武装解除させた上での皆殺し。九千のローマ兵が殺されました。エブロネス族の長は、時を無駄にせず、近隣の部族にローマに反撃するチャンスだと喧伝してまわります。そして、あのキケロの弟、賢兄に対して愚弟と噂され病身でもあったものの、弟思いの兄によってカエサルに託されていた弟キケロが守る冬営地に攻めこみます。ところが弟キケロ、実はなかなかに有能だったのです。ローマ兵六千でガリア兵六万に対します。簡単に落とせないことを悟ったガリア側はまたしても奸計を企み、他の冬営地に行くように勧めます。しかし、弟キケロは「武装した敵の助言を受け入れるのはローマ人のやり方ではない」として突っぱねます。格好良すぎる!しびれます!カエサルをはじめ他の部隊への援助要請も失敗し、なかなか援軍が来ない中で冬営地を死守し続けます。包囲されて七日目、ようやくカエサルの元に急を告げる使者が到着しました。少数であっても強行軍で駆けつけたカエサルは敵を罠にはめ撃破。弟キケロの部隊と合流します。弟キケロの部隊はほとんどが負傷していました。カエサルは一人一人の名前を読んで賞讃したそうです。そしてそのカエサルはいつも身だしなみをきちんとしている人には珍しくひげものび、髪もボサボサ。それをみた兵士たちも感動したそうです。しかし、多くの同僚を失った兵士たちの心の問題が残っていました。カエサルは「あの不幸はサビヌスの浅はかな判断が招いた結果であり、それも諸君の勇気により復讐はなったのだから耐えるしかない」と励ましました。
「後を振り返らない性格の最高司令官に、一兵卒までが染まりはじめていた。」
やっぱり五年(九年)の属州総督任期はこのためか。
ここで文庫九巻は終わりです。次巻ではガリア戦役最大のピンチと鮮やかな逆転劇、そして有名なあの場面が登場します。