こんにちは、Portafortuna♪光琉です。
日中は暑いぐらいの日が続いて、いつ桜が咲いてもおかしくない感じですね。
当店のインスタグラムではすでにご案内しましたが、2025桜アフタヌーンティーの提供期間を少し延長しました。予想していたよりも開花が遅く、当初の予定通りの提供では開花する頃に終了してしまいそうでした。折角の桜アフタヌーンティーが桜の季節に無いなんて!ということで2025桜アフタヌーンティーは4月6日(日)までの提供となります。ぜひお楽しみ下さい。
また、ストロベリーアフタヌーンティーは4月9日(水)からの提供に変更させていただきます。
勝者の混迷・ローマ人の物語Ⅲ その⑥
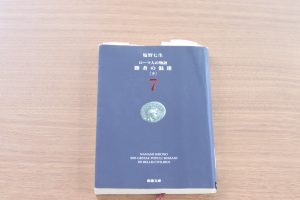
スペインでの「セルトリウス戦役」を終えたローマ、やれやれこれで落ち着いたと言いたいところだったと思いますが、またしても大問題発生です。映画でもお馴染みの「スパルタクスの乱」です。奴隷の蜂起です。ここで塩野さんはまずローマの奴隷について書いてくれています。ギリシア・ローマ時代の美術品や遺跡、哲学、文学に触れると感嘆する。と同時に疑問も抱く「なぜ、非人道的な奴隷制度には疑いさえもたずに生きていけたのか、と。」
本当、疑問ですよね~。現代人だから疑問に思っちゃうのかな?否、今の日本にも技能実習生制度と言う国が作ったれっきとした奴隷制度があるんやから現代人でも疑問に思わん人は思わんハズや。
「はじめに断っておかねばならないが、イエス・キリストは、人間は「神」の前に平等であると言ったが、彼とは「神」を共有しない人間でも平等であるとは言ってくれていない。それゆえ、従来の歴史観では、古代よりは進歩しているはずの中世からはじまるキリスト教文明も、奴隷制度の全廃はしていない。キリスト教を信ずる者の奴隷化を、禁止したにすぎない。」
嫌な感じ、都合ええ理屈やな~。
「キリスト教を信じようが信じまいが、人間には「人権」というものがあるとしたのは、十八世紀の啓蒙思想からである。・・・(中略)・・・とはいえ、法律はできても人間の人間の心の中から、他者の隷属化に無神経な精神までが、完全に取り除かれたわけではないのである。」
「完全に」なんて程遠くまったく取り除かれていませんね、やはり僕にも無神経な精神があるし。
ローマの奴隷市場では奴隷はその価格により八段階に分けられていました。一番高額だったのはギリシア語や弁論術を教える家庭教師でした。ローマ市内の邸宅あるいはナポリ近郊の別荘が買えるぐらいの価格だったそうです。次に医者や建築家、彫刻家、画家といった熟練技術者がきました。一方一番安かったのは子供の奴隷でした。家庭教師と子供の奴隷では価格は100対1もの差がありました。
自由民の二分の一から三分の一もの数の奴隷がいたにもかかわらずローマでは奴隷の蜂起はほとんどありませんでした。その理由として塩野さんは、たとえ奴隷であっても家族の一員として考えられていたことや、解放奴隷になれる制度も整っていたこと、解放奴隷の子供はローマ市民になれたことなどを挙げています。
「古代のローマ人による奴隷の定義は、自分で自分の運命を決めることが許されない人、であった。」
この定義だと天皇陛下をはじめ家業を継がざるを得ない人たちは奴隷ということになるな。今のウクライナの人たちもトランプとプーチンが勝手に話を進めて、自分たちの国の運命を自分たちで決められないようになりつつあることを考えると、しみったれのトランプもクソったれのプーチンもウクライナを自分たちの奴隷とでも思っていやがるのかなと勘ぐってしまいます。
「奴隷には、兵役も税金も免除されていた。自分の運命を自分で決める権利を完全にもっていない人には、義務も課されなかったのである。」
筋が通っていると言えば通っている。
「しかし、義務は課されようとも、自分の運命は自分自身で決めたいと望む人は、奴隷の中にもやはりいた。」
見世物のために日々剣闘士として闘うことを強いられていた奴隷たちがそうでした。スパルタクスを頭領にして集団脱走・武装蜂起したのです。百五十年後の大噴火でポンペイを埋め尽くす前のヴェスヴィオ火山は木が生い茂る山でした。そこに立てこもったスパルタクスたちは山を降りては近隣の農園を略奪し始めたのです。剣闘士たちですから屈強な男たちです。はじめ甘く見たローマ政府は小隊を送って鎮圧しようとしましたが、簡単に返り討ちに合います。小隊とは言えローマの正規軍があっけなく負けた事実を知った南イタリアの農園で働く奴隷たちがスパルタクスたちに合流するようになります。ローマ政府も次は本気で軍を送りますがそれも壊滅。ますますスパルタクスに合流する人々が増えます。その中には奴隷だけでなく、奴隷とさほど差がないないような生活を余儀なくされていた下層の人たちもいました。総勢七万もの勢力となったスパルタクスたち。ローマ政府も本気で鎮圧しようとしますが、負けてばっかり。でも最終的には「特筆に値するほどの軍事的才能の持主ではなかった」クラッススが八個軍団五万の兵を託されなんとか鎮圧することに成功しました。ここでもこの書かれようのクラッスス。
「ローマの覇権は、地中海世界全体をおおうまでになっていた。だが、それがためにかえって、元老院主導によるローマ独自の共和政体を、守りきることがむずかしい状態になりつつあったのである。また、この「スッラ体制」は、指導者階級においてのみ、現実に合わなくなっていたのではなかった。被指導者階級でも、状況は同じであったのだ。」
これまでの体制があったからこそ発展してこられたのに、それを変えないといけない、あるいは捨てないといけない。今まで良かったものを変える捨てるのは難しい、どころか渦中にいるとその必要性に気づくことすら難しいと思います。スッラのところで塩野さんはその捨てる必要性については「ただ一人の、人物を除いて」理解を越えていたと書いてありました。
実際この時にも捨てるまではできなかったローマ。でも変えることの必要性を感じていた人たちもいました。
「この現実を直視し、その打開の必要を悟ったのは、元老院内の良識派と言ってもよい人々であった。」
紀元前七五年担当の執政官の一人ガイウス・アウレリウス・コッタもそうでした。法学者でもあったコッタは元老院を説得した上で、穏健なやり方で改革を実行します。護民官制度の改革や貧民への小麦の低額配給の復活、スッラによる粛清のために公職から追放されていた人たちの公職復帰などです。これらはすべてスッラが行った改革を元に戻すことを意味しました。この時点でまだスッラの死後三年も経っていません。
このように「スッラ体制」は徐々に崩壊していくのですが、最後の鉄槌を下したのは、またしてもスッラ門下生のポンペイウスでした。
スペインでの「セルトリウス戦役」を終え帰国したポンペイウスは軍を従えたままローマ郊外に宿営します。そしてそこから元老院に対して翌年の執政官に立候補できるようにすることなどを要求しました。
スッラの改革により執政官になれるのは四十二歳からと決まっていましたが、ポンペイウスはまだ三十六歳。さらにこの時点でもまだ他の公職を経験していないためにいまだに元老院議員でもありません。ポンペイウスに総司令官の地位を与えてスペインに送り込んだのは、あくまでも特例でした。でも今回は、ポンペイウスは特例を要求したのではなく、自分には執政官になるだけの実力と資格があると主張したのです。年功序列ではなく実力主義を認めろというわけです。このポンペイウスの要求を認めるということは、元老院主導による共和政ローマの維持を狙ったスッラによる改革が全てご破算になることを意味します。
「実力ならば、資格は充分であったろう。だが、実力主義を認めていては、年功序列制を守ることによってしか機能しえない「元老院体制」は、崩壊するしかないのである。」
元老院も抵抗しましたが、武装したままの軍をバックにしたポンペイウスです。ならばと元老院は「スパルタクスの乱」を鎮めたばかりでまだ武装していた軍を従えていたクラッススがポンペイウスを説得してくれることを期待しました。
「ところが、以前からポンペイウスの華やかな活動に嫉妬していたクラッススが、ポンペイウスの説得にまわるどころか、自分も執政官になりたいと言いだしたのである。・・・(中略)・・・クラッススのほうは、元老院議員でもあり法務官の経験もあり、年齢も四十三歳だったから、翌年度の執政官に立候補する資格は充分にある。ただし、この男には人望がなかった。」
トホホなクラッスス。父の代からすでにローマ一の金持ちであったクラッスス。反スッラ派の没収資産の売買でさらに財を貯えました。さらに人の困りごとにつけ入っては儲けるような人間なんです、コイツは。
「このような男に、市民たちの人望が集まるはずがない。しかし、クラッスス自身は、自分のもつローマ一の財力が、ローマ一の政治力にイコールすると思いこんでいた。」
どこまでもトホホな奴。とは言え、自分の不人気を知ってか知らないでか、執政官に立候補はできても市民集会で投票してもらえるかどうかは怪しいと心配する程度には現実的でした。
「かといって、執政官には何としてもなりたいクラッススである。長年いだいてきたポンペイウスへの対抗心も、この機に臨んでは忘れることにしたのである。」
コイツ、本当にダサいな。
ともに名門貴族出身で裕福。実力は充分でも年齢が足りず、公職経験もないのがマイナス面のポンペイウス。年齢と公職経験は充分でも、人望のないクラッスス。この二人が秘密裏に協定を結びます。クラッススが元老院内でポンペイウスの執政官立候補が可能になるように根回しをするかわりに、人気者のポンペイウスの票をクラッススに回すことにしたのです。これで二人とも紀元前七〇年度の執政官に無事選ばれました。
執政官になった二人。その任期の間にさらにスッラ体制の崩壊に手を貸します。護民官の権威と権力の完全復活と陪審員制度改革です。これで完全に「スッラ体制」は崩壊しました。こうなると、あのスッラの大量殺戮も改革もともに無駄な悪あがきだったように思えて仕方ない。
「良くも悪くもはっきりした性格の持主であり、それがために憎まれはしても軽蔑はされなかったスッラだが、その彼には「元老院体制」の再活性化という、確とした政治目標があった。そして、それを実現するには、「票」を気にしていてはできないことを知っていた。彼は「元老院体制」を再び確立すれば、国家ローマが直面している諸問題も解決できると信じていた点ではノスタルジックだったが、それを怠れば、つまりは民衆の思うままに国家を放置すれば、君主政に行きつくしかないと見透していた点では、まれにみるリアリストであった。」
憎まれはしても軽蔑はされない、こういう生き方は格好良いな~。それにしても見透すことができるってすごい人ですよね。
「(ギリシアの歴史家)ツキディデスは、著作「ぺロポネソス戦史」の中で、「大国の統治には、民主政体は適していない」とまで言っている。民主政だけが、絶対善ではない。民主政もまた他の政体同様、プラス面とマイナス面の両面をもつ、運用次第では常に危険な政体なのである。」
もし君主がまっとうな人ばっかりなら君主政の方が実は良いんじゃないのかな?と思うことがあります。でも、まっとうな君主なんてそうそう現れるもんじゃなから実際には良くなくて、だから民主政の方がまだマシなのかな?塩野さんによると、スッラとは違って確とした政治目標があったとはどうも思えないポンペイウスとクラッスス。執政官の間に行った政治をみてもどうもそのフシがある。でも確とした政治目標があろうがなかろうが、統治される側にとって社会が良くなったのだからそれはそれで良かったのではないかと言います。
「彼(ポンペイウス)にしてみれば、必要と思うことをやっただけであって、それも彼の性格からすれば、人々のためになるという善意に裏打ちされていたにちがいない。」
「このように紀元前七〇年は、「スッラ体制」の幕が閉じられる年になった。スッラ自身の死後わずか八年で、彼が築きあげたシステムはことごとく崩壊したのである。おそらく、アウレリウス・コッタ以外は、意識して崩壊させたいとは思わないでやったにちがいない。ただただ、現実が要求することに応えようとして、「スッラ体制」の崩壊に手を貸してしまったのではないか。リーダーに求められる資質のすべてをもっていたスッラだったが、先見性だけはもっていなかったのであろう。」
ポンペイウスの章で一番大切な箇所ですね。スッラが行った改革も結局は時代に合っていなかった。スッラ派がスッラ体制を崩壊させはしたが、それも時代が必要としていたからであって、彼らの個人的野望からではなかった。
先見性、おしいなスッラ。ほっといたら君主政に行きついちゃうことまでは先見できていたのに。
