こんにちは、Portafortuna♪光琉です。
すでに一度ご案内させていただきましたが、2025年4月から定休日を月曜・火曜・金曜に変更させていただきます。
月曜日が祝日の場合は営業いたします。営業時間はこれまで通りです。よろしくお願い致します。
勝者の混迷・ローマ人の物語Ⅲ その⑦
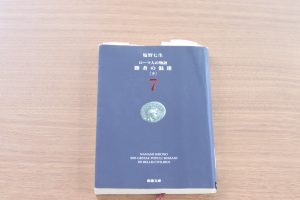
執政官の一年の任期を終えたポンペイウス(とクラッスス)。本来ならば10カ所ある属州のどこかに総督として赴任する決まりがありましたが、ポンペイウスは従いませんでした。ポンペイウスは軍事の天才、紀元前六九年当時、軍を派遣してまで対処しなければならないような所はオリエントしかありませんでした。他は平和だったってことです。そしてそのオリエントにはスッラ門下生としては先輩格であり、スッラからの信頼も特に厚かった、こちらも軍事の天才ルクルスが五年前から送られていたからです。
ルクルスは「大変に貴族的な男だった。書こうが話そうが、ギリシア語とラテン語の完璧な使い手であり、美的価値をわかる眼をもち、教養も深かった。」若くしてスッラにその能力を買われ重要な任務を任せられるなど、順調にキャリアを築いていきました。スッラが死んだときには(推定)三十八歳。その時には元老院内でもすでに有力者であったにもかかわらず、スッラに心酔していたルクルスはスッラの行った改革に忠実に四十二歳になるまで執政官になりませんでした。「執政官時代のルクルスには、政治的な動きはほとんど見られない。・・・(中略)・・・もともとが、政治的なところはあまりなかったルクルスであった。」
好感が持てます。
「ローマが他に力を割かざるをえないと見るや侵略行動を再開するポントス王ミトリダテスだったが、紀元前七三年という年も、ローマにとっては大変な年になっていた。」
スペインでのセルトリウス戦役と、イタリア半島でのスパルタクスの乱の最中でした。
「もちろん、このような好機を見逃すミトリダテスではない。」
ローマ属州ビティニアに大軍を送り込みました。初戦こそ勝ったポントス軍ですが、ルクルスが到着してからは圧倒的に少数のローマ軍に二度にわたり負けます。勝ったルクルスは一気にポントス軍を壊滅させるのではなく、当地の内政整備を優先させました。有能な武将であるとともに有能な官僚でもあることを証明しました。
ルクルスにとって不幸であったのは、配下の兵がもともとモチベーションが低い寄せ集めの兵だったことでした。
「さらなる不幸は、武将の才能に長じ行政官の能力も充分なルクルスであるのに、女運と部下運には恵まれなかったことである。彼の家庭生活は、生涯不幸だった。」
その理由を塩野さんは「コミュニケート不足」だとします。そして、部下との間もコミュニケートが不足していたとします。
「ルクルスは、努めて兵士たちと交わり、行軍でも戦闘でも常に先頭に立ち、野営をしなくてはならない地方では、総司令官の彼も、兵士たちと同じ条件で野に寝た。それでも、兵士たちは彼に不満だった。ただ、闘うと勝つから、不承不承にしても従いて行ったのである。」
ここを読んでいる限り気の毒なルクルスです。
二度もルクルスに敗れたミトリダテスは、隣国アルメニアと共闘体制を築きます。アルメリアに攻め入ったルクルスをアルメリア王は嘲笑します。ところがその闘いはルクルスの圧勝でした。アルメリア側戦死者十万以上に対しローマ側戦死者5人。本来ならこの勢いをかってミトリダテスの息の根を止めたかったルクルスですが、配下の兵たちが進軍を拒否します。
「ルクルスは、自らの才能の優秀さに自信をもっていた。それはそれで悪くないが、優秀な自分が耐えているのだから、兵士も同じく耐えるべきと考えていたのである。」
兵士に厳しい行軍を強いるにはそれを納得させる必要があるにもかかわらず
「ルクルスは、この種の「コミュニケート」の重要性を知らなかった。・・・(中略)・・・心の通い合いの大切さに気づかなかったのであった。」
優秀な人にだけ用意されている落とし穴ですね。さらに、
「この、総司令官と部下たちの精神的な相互関係の欠如は、戦利品の分配にもあらわれた。」
当時のオリエントは西欧よりもよっぽど豊か。戦利品も莫大でした。
「ルクルスは、部下の兵士たちに、銀貨ならば応分に分け与えた。ただし、美術工芸品は、自分のものにした。このようなものは、庶民である一般兵士には価値はわからないと思っていたからである。ルクルスの判断は正しかったであろう。また、価値のわかるルクルスによってこれらがローマに送られたことで、人類の財産である芸術品が、どれだけ後世にまで生き残れたことか。しかし、このような場合は、一般の兵士にも、彼らが不満を感じないような処置をほどこしておくべきであった。・・・(中略)・・・だが、ルクルスはそれをしなかった。しなかったどころか、国庫に納入する以外の金貨は自分のものにしてしまった。総司令官には、当然の報酬であるというわけだ。」
これはやり方が浅はかでしたね、恨まれても仕方ないな。
「自らの優秀さに自信をもち、自分のやることは正しいと信じて疑わないルクルスは、話せばわかる、としか考えなかった。彼は、兵士たちを集めて、ミトリダテスの息の根を止めるのに今は好機だと言って説得に努めた。しかし、総司令官は私腹を肥やすことしか考えないと思いこんでしまった兵士たちは、もはや彼には従おうとはしなかった。」
こうなるとルクルス気の毒と思いもするけど、ルクルスに問題あるわなとも思います。
兵士たちに従軍を拒否されたルクルスは結局、一敗もしないで後退せざるを得ませんでした。
一方ローマでは、三十九歳になったポンペイウスが活動を再開し始めていました。
ローマが地中海に広く覇権を広げるにつれてローマ人が海に出ていく機会が格段に増えました。地中海では古くから海賊が悪さをしでかしていて、海に出ていく機会が増えたローマ人たちもその被害を受けることが多くなってきていました。その海賊に目をつけたのがポントスのミトリダテスでした。海賊に資金を提供し、ローマの兵や武器などを載せた船を襲撃させたのです。ローマに輸入される小麦もおぼつかなくなり海賊はローマ社会にとって不安の種になっていたのです。
この海賊一掃に名乗りを上げたのがポンペイウスでした。護民官ガビアヌスに働きかけ、市民集会の場で海賊一掃をポンペイウスに一任することを可決させました。総司令官ポンペイウスの下には兵十二万五千を投入する、作戦実施期間として三年間をポンペイウスに与える、ローマの国家予算の七割にものぼる軍資金を拠出することなども議決されました。
「前代未聞のことばかりしてくれるポンペイウスに、またもその形容をくり返さねばならないが、これもまた前代未聞のことであった。・・・(中略)・・・ローマ人はいったん決めれば断固として実行する性質をもっていたが、それにしても大決心であった。」
やるからには徹底的、そして何が何でもやり通す。良いな~。
これが決定されるとすぐに高騰していたローマの小麦価格が急落しました。
「「スッラ体制」はこれで、最後の息の根まで止められたのである。」
またしてもスッラ派のポンペイウスによってですね。
「ポンペイウスによる海賊一掃作戦は、後世の軍略家たちが一致して賞讃するのを待つまでもない、戦略の見本ともいうべき傑作になった。」
作戦実施海域を十三に分け、さらに作戦期間も前後の二期に分けて作戦を実施していったのです。
「弱い敵から倒していくのは、戦略戦術の基本でもある。」
僕も仕事は簡単なもの、やっつけ仕事でいいものから先にやって、じっくりやらないといけないものはその後でするようにしています。ひょっとすると僕にも総司令官の才能があるかも!
三年を与えられたポンペイウスですが、なんと八十九日間でやり遂げてしまいました。地中海から海賊は一掃され、安全な海に戻ったのです。海賊に悩まされていたギリシア人なんてポンペイウスを神とさえ呼んだそうです。最近の日本でも神と呼ばれる人がそこかしこにいますね。どっちも多神教だから。
その後のポンペイウスの動きを見ると、「ポンペイウス、お前初めっから三年もかかるなんて思ってなかったやろ?八十九日は出来過ぎとしてもええとこ一年ぐらいと思っとったんとちゃうの?本当の狙いはこの次の任務やったんやろ?絶対そうや!」と言いたくなります。たとえそうであったとしても別に悪いとは思いませんが。
ポンペイウスはまた護民官ガビアヌスに働きかけ、オリエントにいるルクルスを解任して自分を代わりの総司令官にするようにさせました。
ルクルスからポンペイウスへの指揮杖の移譲に際しては、互いに相手を非難し合いました。
「解任されて帰国の途に着くルクルスに、ポンペイウスは、帰国後の凱旋式に必要であろうと言って、自分が引き継ぐルクルス下の軍団兵の中から、一千六百の兵を連れて帰ることを許可した。しかし、港に待つ船に乗船したルクルスが眼にしたのは、これ以上闘うことが無理な老兵か、そうでなければ重傷の身の兵士か、または、海賊よりも悪質な、不服従で知られた兵士の一千六百であったのだ。若くして成功し、失敗も挫折も知らないポンペイウスは、このような場合でも平然と冷酷であることができる男だった。」
こういうところがポンペイウスに惹かれない理由です。総司令官なんやから冷徹であることは求められますが、冷酷なんはどうかと思いますね。いらん兵士を一緒に連れて帰ってもらいたいんならそう言ったらええやん。凱旋式に必要やろなんて良い人ぶって。嫌いやわ。
七年ぶりにローマに帰国したルクルスは、ローマの男にとって最高の栄誉である凱旋式を盛大に執り行ってからは、徐々に政界から離れていきました。そして、
「中近東からもち帰ったギリシアの美術工芸品を陳列するために、壮麗な邸宅を各所に建てる。」
共和政時代のローマ人の住まいは、後の帝政時代に比べて質素でした。
「帝政時代の豪邸と比肩できるのはルクルスの屋敷のみ、と言われたのだから、ルクルスの豪奢ぶりも想像がつくというものである。」
独り占めした金貨を使って建てた屋敷で、独り占めした美術品を飾ったのねルクルスさん。どんな屋敷やったのか想像するとワクワクします。どんな美術品が並んどったんやろ?プライベート美術館というレベルやなくて普通に美術館というレベルやったんやろな~きっと。
「集めた芸術品や書物を愉しむのを、他人にも開放する。ルクルス邸内の図書館は、それに関心をもつローマ人や、ローマ在住のギリシア人の寄り集うサロンになった。」
「しかし、ルクルスの名が後世でも使われる代名詞になったのは、彼の実践した美食によってである。現代でも西欧では、豪華な美食を「ルクルス式」と呼ぶ。」
ルクルス式か、聞いたことないな、でもめっちゃ魅力的やな~。いつの日か「こういう〇〇なティータイムのことを“ポルタフォルトゥーナ♪式”と呼ぶ」といわれるようになれたら良いな~、世界中で。
「食事をとるということは彼にとって、ただ単に食べることを意味しなかった。食事をとる部屋の装飾、食事中に奏せられる音楽、読みあげられる詩文、食卓で交わされる会話、それに適した客の選定、これらすべての調和ある総合が、ルクルスにとっての「食」であったのだ。」
映画で観る貴族の食事風景ですね。教養も美的センスも問われるから普通の人では到底真似できませんね。
ある時のことです、(たぶん)ポンペイウスがオリエントから帰国した後の話(やと思います)。キケロとポンペイウスはフォロ・ロマーノを歩くルクルスを見かけます。
「共和政時代のローマ人は、いかに元老院で口角泡をとばして議論しあっても、また政治信条がはっきり反対とわかっていても、いったん私的な場所となると肝胆をひらいて付き合うのが良いところだったが、キケロはともかくポンペイウスも、ルクルスを見て見ない振りなどはしなかったのである。」
不思議というか、面白いというか、良い慣習ですね。でも日本人は苦手ですよね、多分。僕は無理ですね。
キケロとポンペイウスは、もちろん上層階級の礼節を守りつつのことでしょうが、要するに「今晩ルクルスさん家行ってええ?晩御飯食べさせて欲しいんさ。だって「ルクルスは美味いもんばっか喰っとる」って噂になっとるやん。ご相伴にあずかりたいの。ただ私たち二人のために特別に用意するんやなくて、ルクルスさんが普段食べとるのと一緒のもの食べたいだけやで、特別なもの用意せんといてね。」ということやったんです。
二人のこの押しかけ招待を受けたルクルス。その日の晩餐は召使いに命じて最上級のものを用意したそうですが、その一食にかけた費用は、一般庶民の年収の10倍だったそうです。一般庶民の年収が300万円としたら3000万円!何の食材使って、どんなメニュー作ったら3000万円の晩餐できんねん!おまけにその日やで、準備できるんかい!僕も呼んで欲しかったわ~。でも手ぶらで行くわけにもいかんし、手土産どうしたらいいのか悩むな。
「しかし、いかに熾烈な政争に明け暮れようと、共和制時代のローマ人には、質実剛健であることを誉め讃え、豪奢な私生活は軽蔑する傾向が強かった。ルクルスの豪奢は、人々を驚かせはしたが、尊敬はされなかったのである。だが、政界に未練のないルクルスには、そのようなことはどうでもよいことであった。」
貴族のローマ人と言えば、演奏を聴きながら、奴隷に用意させた食事を寝そべって食べ、吐いてはまた食べるという享楽的なイメージがないですか?あれは後の帝政時代のことのようです。人からどう思われようが気にせずに自分の楽しみを追求するルクルス、好きやわ~。
「あくまでも私生活の愉楽に徹した十年を過ごした後、ルキウス・リキニウス・ルクルスは死んだ。・・・(中略)・・・ルクルスの葬式は、市民たちに特別な感情を巻き起こさないままに始まって終った。・・・(中略)・・・副将をしていた時期が、最もよく能力を発揮できた男も死んだ。」
最後楽しみ尽くして静かに逝く、ルクルスの生き方いいな~。優秀な副将が得た将のスッラはやはりフェリックスでしたね。
